NHKスペシャル「未完のバトン 第5回 人生の最期と希望」を見て
先日、NHKスペシャル 「未完のバトン 第5回 人生の最期と希望」 を見ました。自分の死をどう迎えるか――私はこのテーマに強い興味があります。なぜなら「1人でちゃんと生きて、1人でちゃんと死にたい」と思っているからです。私の考えとしては「死ぬタイミングは自分で選びたい」というものです。
番組の中で紹介されていたのが、市橋亮一医師です。岐阜県で15年以上にわたり多方面のスタッフと共に総合在宅医療クリニックを運営し、終末期医療について考えるために多くの国を訪れてきた方です。
市橋医師は「死が間近に迫った状態でも、キラッと輝く瞬間はある」と語り、安楽死の選択肢のある社会には否定的な立場を取っているように見受けられました。この番組を通じて、イギリス・フランス・オランダなどいくつかの国で安楽死が認められていることを知り、私のような考えを持つ人が世界には多いのかもしれないと感じました。市橋医師は、安楽死の認められた国に行って、その国の意思とも意見を交わされていました。また、死を迎える日までどうしたら生きがいを持って生きられるか、いろいろな国の医師と終末期医療のあり方を模索されて、自分のクリニックで試されていました。先日まで放送されていたドラマ「19番目のカルテ」を思い出し、現実社会でもこんな医師が増えるといいな・・・と思いました。
番組には、7年前に安楽死を選択した夫を持つ女性が登場しました。その夫は病気と闘いながら様々な治療を試み、最後に「もう限界だ」と海を見ながら呟いたそうです。夫の死から7年経った今も、その妻は深い苦しみを抱えていました。
この場面を見て、私は考えさせられました。未婚・子なしの私は自由で、両親が亡くなった後は「死んでほしくない」という家族もいないでしょう。書きながら少し寂しさを感じましたが、それもまた事実です。
しかし、安楽死を選ぶ本人にとっては幸せな選択であっても、残される家族にとっては別の重みがあるのかもしれません。「大切な人の気持ちを尊重することは、果たして愛情なのか?」という問いを残された家族は突きつけられることになる。
一つのケースを見ただけでも課題が見えてくるように、安楽死には様々な問題が伴います。日本は慎重な国ですので、私が生きているうちに安楽死が認められるかどうかは分かりません。
番組に登場した、安楽死が認められた国へ渡った俳優さんの言葉が印象的でした。
「生と死は相反するものではなく、一緒に存在するもの」
「どういう死を迎えるかを考えることは、生きることを考えること」
この言葉が、妙に腑に落ちました。
「どう死ぬか」と同じくらい「どう生きるか」が大事
結論として、安楽死が認められるべきかどうかは、今の私には「分からない」という答えになりました。でも、死を意識することで残された人生を一日一日大切に過ごせる気がします。人生最期の日に「いい人生だったな」と思いながら、静かに人生を終えられるようにしたいです。
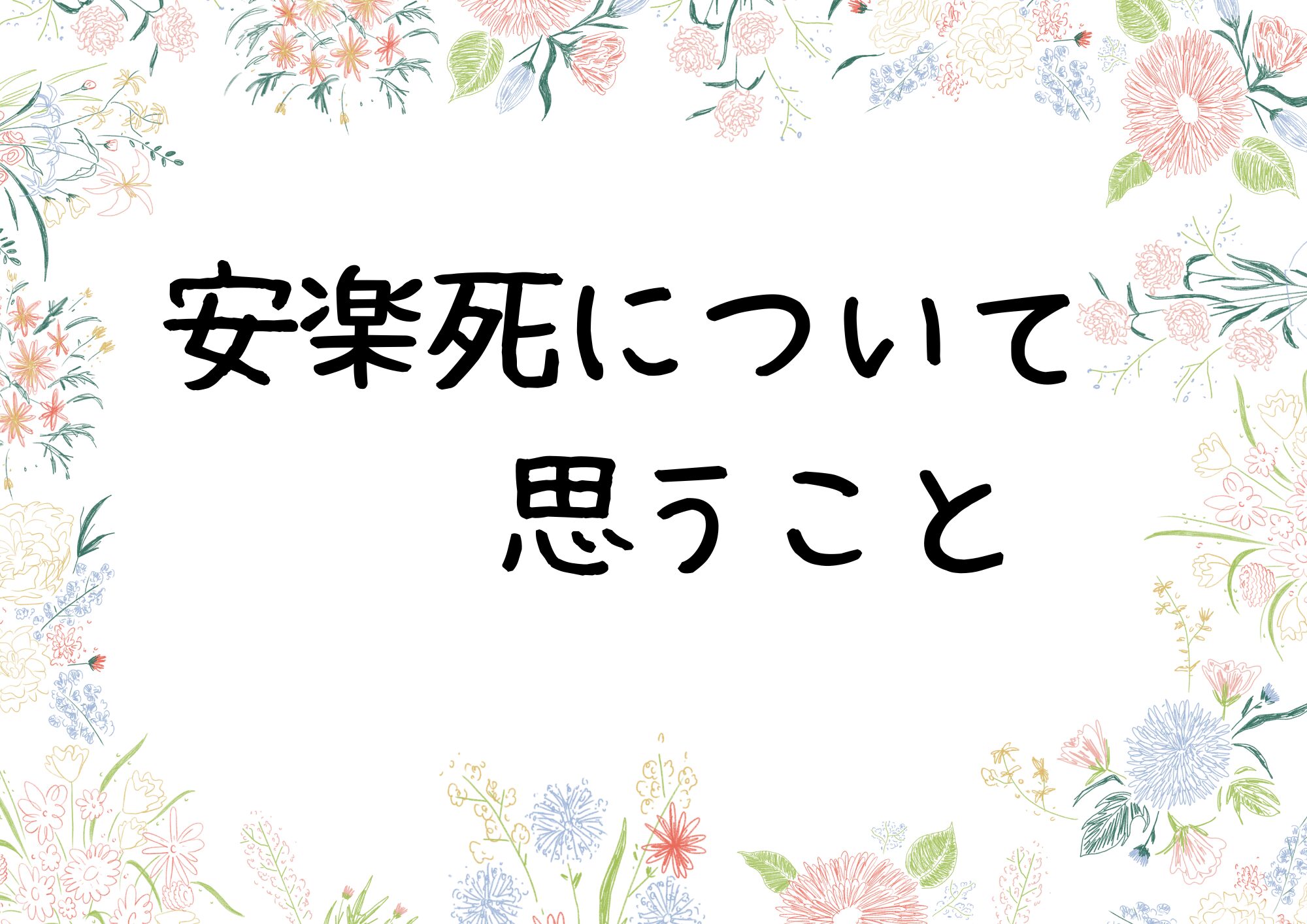
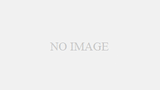

コメント